認知症とは
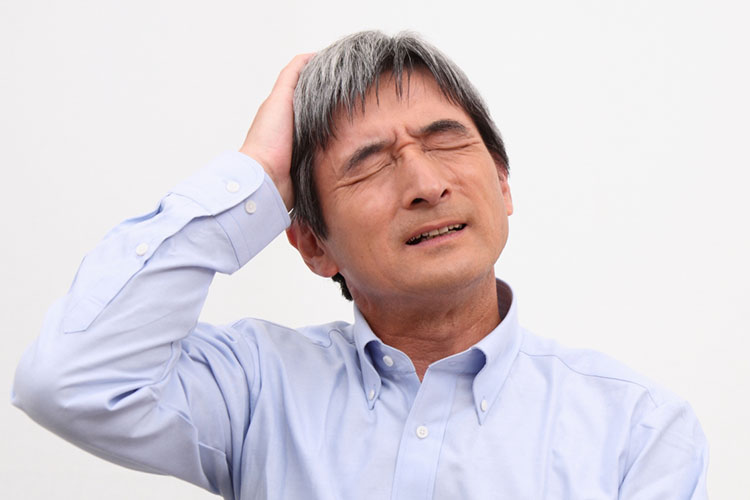
認知症とは、一度正常に発達した脳機能が低下し、記憶や判断力、理解力などが徐々に低下していく病気です。単なる「もの忘れ」とは異なり、日常生活に支障をきたすほど認知機能が低下するものです。認知症にはさまざまなタイプがあり、進行速度や症状の現れ方が異なりますが、早期発見と適切な対応によって、進行を遅らせることや、生活の質を保つことが期待できます。
現在、本邦では高齢化が進んでいることで、認知症の患者様の数も増加しています。厚生労働省の報告によると、65歳以上の高齢者において2022年時点では、認知症高齢者数は443.2万人(12.3%)、軽度認知障害(MCI)高齢者数は558.5万人(15.6%)となっており、現在も増加し続けています。
初期に現れる
認知症の症状
認知症は、早期に気づくことで進行を遅らせることができます。認知症の初期には以下のような症状がみられることがあります。日常生活においてこのような事柄に気付きましたら、当院にお早めにご相談ください。
- 物忘れが増える
- 昨日の夕食を思い出せない、同じ話を何度もするなど
- 時間や場所の感覚があいまいになる
- 今日が何日かわからない、慣れた場所で道に迷うなど
- 判断力の低下
- お金の計算ができない、服装が季節に合っていないなど
- 日常生活のミスが増える
- ガスの火を消し忘れる、料理の手順を間違えるなど
- 性格や行動の変化
- 怒りっぽくなる、急に無気力になるなど
- 興味や関心がなくなる
- 趣味をやめる、人と会うのを避けるなど
認知症の中核症状と行動
・心理症状(BPSD)
認知症の症状は、大きく分けて「中核症状」と周辺症状である「行動・心理症状(BPSD)」の2種類があります。中核症状は脳の障害による基本的な症状を指し、周辺症状は行動や心理の変化を指します。
中核症状
中核症状とは、脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状で、記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下・実行機能障害、失語などがあります。日常生活において見られる症状としては以下のようなものがあります。
- 記憶障害
- 新しいことを覚えられない、昔のことは覚えているなど
- 見当識障害
- 時間・場所・人がわからなくなるなど
- 理解・判断力の低下
- 話の内容が理解できない、物事の順序がわからなくなるなど
- 実行機能障害
- 料理の手順がわからなくなる、計画を立てられないなど
- 失語・失行・失認
- 言葉が出にくい、物の名前を忘れる、着替えられない、家族が分からなくなるなど
行動・心理症状(BPSD)
BPSDとは、本人の性格、環境、人間関係などの要因が絡み合って、精神症状や日常生活における行動上の問題が起きる症状や行動異常です。主なものとしては、不安・抑うつ、徘徊、幻覚・錯覚、妄想、失禁、暴力・暴言、睡眠障害などがあります。これらは認知症において、患者様本人やご家族様に対し、中核症状よりも深刻な状況を招く場合がありますので、お早めに当院にご相談ください。
詳しくはこちら
認知症の主な種類と原因
認知症をきたす疾患として少なくとも数十は挙げられますが、罹患者数が最も多い神経変性疾患群にはいくつかの疾患があり、原疾患によって症状の現れ方が異なります。主な疾患として、「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「脳血管型認知症」「前頭側頭型認知症」などがあります。
アルツハイマー型認知症
脳にアミロイドβという異常なタンパク質が蓄積し、神経細胞が破壊されることにより発症すると考えられています。認知症の中では最も多く、全体の約50%となっています。発症初期には、いわゆる「もの忘れ」である記憶障害が初期にあらわれ、それが徐々に進行していきます。
症状例
- もの忘れが目立つ(昨日の出来事を思い出せない)
- 時間や場所がわからなくなる
- 言葉がうまく出てこない
- など
レビー小体型認知症
脳に「レビー小体」と呼ばれる異常なたんぱく質がたまることによって神経の情報伝達が円滑にできなくなり発症すると考えられています。手足の震えや体のこわばりなど、パーキンソン病と似た症状が現れることが多いのが特徴です
症状例
- はっきりした幻視(「小さい子どもがいる」など)がある
- 眠っているときに大声を出したり、手足を動かしたりする(レム睡眠行動障害)
- 体が動きにくくなる(転びやすくなる)
- など
血管性認知症
脳梗塞や脳出血により、脳の血流が悪くなり、神経細胞が損傷を受けることで発症するものです。低下した認知機能と正常な認知機能が存在する「まだら認知症」という状態になることや、安定していると思ったら突然、急速に悪化するという「階段状の進行」がみられることも特徴です。
症状例
- 突然の記憶障害や言葉の障害
- 感情のコントロールが難しくなる(すぐ泣いたり怒ったりする)
- 手足が動きにくくなる
- など
前頭側頭型認知症
脳の前頭葉や側頭葉にピック球という変性したたんぱく質があらわれ、脳が萎縮することで発症すると考えられているものです。比較的若い世代で発症することが多く、性格の変化や過食や窃盗、暴力など、衝動的な行動が目立つようになります。
症状例
- 周囲を気にせず突然怒る、暴力をふるう
- いつも同じものを食べ続ける
- 何時間も歩き続ける
- など
認知症の治療
認知症の治療は、原因や症状のあらわれ方によって異なりますが、薬による治療や生活環境の整備やさまざまなリハビリテーションなどによって症状の改善を図るようにします。
薬による治療としては、中核症状に対しては抗認知症薬が、行動・心理症状(BPSD)に対しては抗精神病薬や抗うつ薬、抗不安薬、抗てんかん薬などの向精神薬が用いられることがあります。
近年、アルツハイマー型認知症に対する新薬であるレカネマブやドナネマブも承認されていますが、これは軽度認知障害(MCI)と軽度認知症が対象となっています。詳しくは当クリニックの医師にお尋ねください。
また、日常生活において食事や運動、入浴などを、できるだけ自力で行うことにより、認知機能を維持していくことが重要で、そのための生活環境の整備が大切になります。また「回想法」や「芸術法」「運動療法」「現実見当識訓練」など、さまざまなアプローチによる認知機能の維持も、認知症の治療では重要になります。
当クリニックでは、患者様それぞれの状態や、ご家庭の環境に合わせて、治療法を検討していきます。ご自身やご家族に、少しでも不安な症状があったり、わからないことがあったりした場合は、お気軽にご相談ください。
